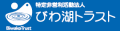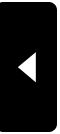近年の琵琶湖をめぐる環境課題 vol.2
2009年10月02日
2007年、合同調査のはじまり
3月といえば、普通の年ならば琵琶湖は冬の循環期を迎え、深層まで溶存酸素が回復している季節である。が2007年はまだ循環が起こっていなかった。2007年3月10日、この状況に危機的なものを感じた研究者たちが「琵琶湖の全循環と湖底の酸素濃度に関する研究会」を開いた。この研究会では、滋賀県立大学、滋賀県琵琶湖環境科学研究センター、滋賀県水産試験場、京都大学、滋賀大学などに所属する研究者が集まった。つづく4月3日に合同研究会を開催し、2007年の循環の過程を検証し今後の対応(具体的には琵琶湖深層の溶存酸素濃度の監視)を協議した。これらの研究会がきっかけとなって、関連した研究者らが協力して調査を進める基盤が作られていった。2007年度は、筆者を含む滋賀県立大、京大生態研、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターが中心となって合同調査を行なった。

琵琶湖は大きな湖なので、1船の調査ではその広域を網羅できない。琵琶湖周辺には船を持っている研究機関が複数存在する。そこで、琵琶湖周辺の複数の研究機関に所属する研究者有志が同時に調査船を出し、観測地点を分担して調査を行った。このときは深層の溶存酸素濃度低下が問題になっていたので、酸素濃度の低下が懸念される、北湖第一湖盆の深部を網羅する形で観測を行った。このような調査は数ヶ月に1度、循環期となる冬場にはほぼ毎月行われた。普段個別の研究をしている研究者らが、何の研究資金もなく集結し、手弁当で連続的な調査を行ったことは、琵琶湖の研究史上でも画期的なことであったらしい。そこには、琵琶湖で起こるかもしれない危機的な状況を、タイミングを逃さず観測し捉える必要があるという強い意志があった。結果、この広域的な調査を継続したことにより、この後、琵琶湖のどのあたりに酸素濃度が低い水塊が分布しているのかを詳細に捉えることができることとなる。
この文章は、2008/8 地理に掲載された原稿を元に、作者長谷川氏の許可を得てアップしています.
古今書院HP
http://www.kokon.co.jp/
「地理」53巻8月号目次
http://www.kokon.co.jp/5308-m.pdf
3月といえば、普通の年ならば琵琶湖は冬の循環期を迎え、深層まで溶存酸素が回復している季節である。が2007年はまだ循環が起こっていなかった。2007年3月10日、この状況に危機的なものを感じた研究者たちが「琵琶湖の全循環と湖底の酸素濃度に関する研究会」を開いた。この研究会では、滋賀県立大学、滋賀県琵琶湖環境科学研究センター、滋賀県水産試験場、京都大学、滋賀大学などに所属する研究者が集まった。つづく4月3日に合同研究会を開催し、2007年の循環の過程を検証し今後の対応(具体的には琵琶湖深層の溶存酸素濃度の監視)を協議した。これらの研究会がきっかけとなって、関連した研究者らが協力して調査を進める基盤が作られていった。2007年度は、筆者を含む滋賀県立大、京大生態研、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターが中心となって合同調査を行なった。

琵琶湖は大きな湖なので、1船の調査ではその広域を網羅できない。琵琶湖周辺には船を持っている研究機関が複数存在する。そこで、琵琶湖周辺の複数の研究機関に所属する研究者有志が同時に調査船を出し、観測地点を分担して調査を行った。このときは深層の溶存酸素濃度低下が問題になっていたので、酸素濃度の低下が懸念される、北湖第一湖盆の深部を網羅する形で観測を行った。このような調査は数ヶ月に1度、循環期となる冬場にはほぼ毎月行われた。普段個別の研究をしている研究者らが、何の研究資金もなく集結し、手弁当で連続的な調査を行ったことは、琵琶湖の研究史上でも画期的なことであったらしい。そこには、琵琶湖で起こるかもしれない危機的な状況を、タイミングを逃さず観測し捉える必要があるという強い意志があった。結果、この広域的な調査を継続したことにより、この後、琵琶湖のどのあたりに酸素濃度が低い水塊が分布しているのかを詳細に捉えることができることとなる。
この文章は、2008/8 地理に掲載された原稿を元に、作者長谷川氏の許可を得てアップしています.
古今書院HP
http://www.kokon.co.jp/
「地理」53巻8月号目次
http://www.kokon.co.jp/5308-m.pdf
第7話 びわ湖への想い
第4話 深底部での酸素低下はなぜ起こるか
第3話 温暖化によって弱体化する湖の循環
第2話 顕在化するアオコ毒による生物への影響
第1話 琵琶湖に忍び寄る温暖化の波
近年の琵琶湖をめぐる環境課題 vol.6
第4話 深底部での酸素低下はなぜ起こるか
第3話 温暖化によって弱体化する湖の循環
第2話 顕在化するアオコ毒による生物への影響
第1話 琵琶湖に忍び寄る温暖化の波
近年の琵琶湖をめぐる環境課題 vol.6
Posted by びわ湖トラスト事務局 at 14:08│Comments(0)
│琵琶湖