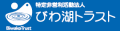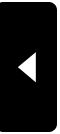第3話 温暖化によって弱体化する湖の循環
2009年11月16日
第3話 温暖化によって弱体化する湖の循環 熊谷道夫
1.琵琶湖の深呼吸
滋賀大学名誉教授の岡本巌氏は、冬に琵琶湖の水が上下によく混合し、湖底の酸素濃度が回復することを、「深呼吸」と呼びました。この混合を、陸水学では全循環と言います。琵琶湖は、一年に一度、深呼吸をする「一回循環湖」として知られています。これとは別に、冬に湖面が凍結するバイカル湖などは、凍る前後の秋と春に、二回循環します。また、熱帯地方にある湖は、表面の水温が常に湖底の水温より暖かく、一年を通じて、全循環することはありません。
では、どのようにして、琵琶湖は深呼吸するのでしょうか。湖底付近の酸素の少ない水を、酸素の豊富な表面の水で置き換えるには、エネルギーが必要です。そのエネルギーを供給するのは、気温の低下です。秋から冬にかけて、季節風の吹き出しとともに、湖面や湖岸が冷却されます。また、湖内に流入する融雪水の影響も無視できません。これらを整理すると、図1のようになります。
最近の研究によると、湖底に冷たい水を供給するのにもっとも効果的なのは、湖岸冷却だと言われています。しかし、冷たい河川水の流入や、強い風のはたらきが、表面の冷たい水を効率的に下方に運ぶという研究もあります。

図1:琵琶湖の全循環が起こる仕組みです。湖面の水が冷やされる場合、そして、川から冷たい融雪水がもぐりこむ場合が考えられます。
2.密度流
1月から2月にかけての河川水は、湖水より密度が重い場合が多く、湖岸周辺の冷たくなった水を巻き込んで潜り込むので、河川から供給される以上の冷水を湖底に運ぶことがわかってきました。
また、1mから2mの厚さで湖底に沿って湖心に流れ込む河川水は、湖底近くに冷たくて酸素の多い水の薄い膜を形成し、湖底泥の影響が直接湖水に及ぶのを抑制する効果を持っているので、たとえ河川からの供給量が少なくても琵琶湖の環境にとってはとても重要だと言えます。
このように、密度の重い水が、軽い水の下に潜り込む流れを、密度流と呼びます。琵琶湖では、たとえば、冬期には、南湖の水が冷やされて、北湖に向かって逆流します。その量は大きく、毎秒数百トンに及ぶといわれています。しかし、琵琶湖で完全に全循環が起こるには、ほぼ1ヶ月にわたって、毎秒数千トンの水の入れ替わりが必要なのです。これは膨大なエネルギーです。
姉川から流れ込む融雪水も密度流です。この場合、河川水と湖水の密度差はあまり大きくないので、湖底まで到達しないという意見があります。しかし、それは正しくありません。密度流が湖底に沿ってどのように流入するかは、密度差だけで決まるのではなく、貫入する水の流速にも依存しています。密度差が小さくても、流れがゆっくりしていれば、湖底まできれいに水は流れ込みます。逆に、密度差が大きくても、流れが速ければ、周りの水を巻き込みやすいので、途中で上昇し始めます(写真)。このように、微妙な流れと密度のバランスによって、融雪水は湖に潜り込むのです。

写真:密度流の実験。左は底まで届くが、右は途中までしか届きません。
なぜ、このような違いが起こるのでしょうか。
3.デッドゾーンの増加
湖底や海底の溶存酸素濃度が低下した水域のことを、デッドゾーン(死の水域)と呼んでいます。つまり、魚貝類の生息に適さない場所ということです。サイエンスに掲載された論文によると、1990年代に入ってから、このようなデッドゾーンの数が世界中で急速に増えています(図2)。一体、何が起こっているのでしょうか。
溶存酸素濃度が減少する理由には、酸素消費の増加と、酸素供給の減少が挙げられます。溶存酸素の多くは、湖底にたまった有機物がバクテリアによって分解されるときに消費されますから、たとえば富栄養化が進行して、湖底に多くの有機物が堆積した場所は、酸欠になりやすいのです。一方、酸素の供給は、先ほど述べた冬期の循環に依存しています。
最近のように、地球温暖化が進行すると、冬期の気温が下がらなくなり、全循環が発生しなくなるので、湖底まで酸素が供給されにくくなります。溶存酸素の低下は、生物の斃死をもたらすだけでなく、底にたまった栄養塩や重金属の溶出をもたらします。人間で言えば、心不全の手前といえます。琵琶湖が、まさにこのような状況に差しかかりつつあることを、私たちは今、深刻に捉え警告を発しています。

図2 これまで学術雑誌で報告されたデッドゾーンの積算数。
10年毎の階数で表示している。1960年以降は、10年ごとに2倍ずつ増加している。
(Diaz and Rosenberg,2008を改変)
一口メモ
水の混合
水は、なかなか混じりにくい性質を持っています。たとえば、アマゾン川には白い川と黒い川があり、両方の川が出合ってからも、数キロにわたって混じりあうことなく平行して流れます。琵琶湖でも、高時川と姉川が合流すると、色の濃さの違った水がずっと下流まで流れていきます。水が混合するためには、お風呂の水をかき混ぜるように、何かの力が必要です。それは、風の力だったり、水流の強さだったりします。混じりやすい状態のことを物理学では、不安定な状態と呼んでおり、よく混合した水の中では、密度はほぼ一定です。一方、安定な状態の水は混じりにくいといえます。地球温暖化が進行すると、海洋や湖沼の表面水は熱せられて、安定になります。こうして、上下に混合しにくくなるので、底では酸素不足になりやすいのです。
1.琵琶湖の深呼吸
滋賀大学名誉教授の岡本巌氏は、冬に琵琶湖の水が上下によく混合し、湖底の酸素濃度が回復することを、「深呼吸」と呼びました。この混合を、陸水学では全循環と言います。琵琶湖は、一年に一度、深呼吸をする「一回循環湖」として知られています。これとは別に、冬に湖面が凍結するバイカル湖などは、凍る前後の秋と春に、二回循環します。また、熱帯地方にある湖は、表面の水温が常に湖底の水温より暖かく、一年を通じて、全循環することはありません。
では、どのようにして、琵琶湖は深呼吸するのでしょうか。湖底付近の酸素の少ない水を、酸素の豊富な表面の水で置き換えるには、エネルギーが必要です。そのエネルギーを供給するのは、気温の低下です。秋から冬にかけて、季節風の吹き出しとともに、湖面や湖岸が冷却されます。また、湖内に流入する融雪水の影響も無視できません。これらを整理すると、図1のようになります。
最近の研究によると、湖底に冷たい水を供給するのにもっとも効果的なのは、湖岸冷却だと言われています。しかし、冷たい河川水の流入や、強い風のはたらきが、表面の冷たい水を効率的に下方に運ぶという研究もあります。

図1:琵琶湖の全循環が起こる仕組みです。湖面の水が冷やされる場合、そして、川から冷たい融雪水がもぐりこむ場合が考えられます。
2.密度流
1月から2月にかけての河川水は、湖水より密度が重い場合が多く、湖岸周辺の冷たくなった水を巻き込んで潜り込むので、河川から供給される以上の冷水を湖底に運ぶことがわかってきました。
また、1mから2mの厚さで湖底に沿って湖心に流れ込む河川水は、湖底近くに冷たくて酸素の多い水の薄い膜を形成し、湖底泥の影響が直接湖水に及ぶのを抑制する効果を持っているので、たとえ河川からの供給量が少なくても琵琶湖の環境にとってはとても重要だと言えます。
このように、密度の重い水が、軽い水の下に潜り込む流れを、密度流と呼びます。琵琶湖では、たとえば、冬期には、南湖の水が冷やされて、北湖に向かって逆流します。その量は大きく、毎秒数百トンに及ぶといわれています。しかし、琵琶湖で完全に全循環が起こるには、ほぼ1ヶ月にわたって、毎秒数千トンの水の入れ替わりが必要なのです。これは膨大なエネルギーです。
姉川から流れ込む融雪水も密度流です。この場合、河川水と湖水の密度差はあまり大きくないので、湖底まで到達しないという意見があります。しかし、それは正しくありません。密度流が湖底に沿ってどのように流入するかは、密度差だけで決まるのではなく、貫入する水の流速にも依存しています。密度差が小さくても、流れがゆっくりしていれば、湖底まできれいに水は流れ込みます。逆に、密度差が大きくても、流れが速ければ、周りの水を巻き込みやすいので、途中で上昇し始めます(写真)。このように、微妙な流れと密度のバランスによって、融雪水は湖に潜り込むのです。

写真:密度流の実験。左は底まで届くが、右は途中までしか届きません。
なぜ、このような違いが起こるのでしょうか。
3.デッドゾーンの増加
湖底や海底の溶存酸素濃度が低下した水域のことを、デッドゾーン(死の水域)と呼んでいます。つまり、魚貝類の生息に適さない場所ということです。サイエンスに掲載された論文によると、1990年代に入ってから、このようなデッドゾーンの数が世界中で急速に増えています(図2)。一体、何が起こっているのでしょうか。
溶存酸素濃度が減少する理由には、酸素消費の増加と、酸素供給の減少が挙げられます。溶存酸素の多くは、湖底にたまった有機物がバクテリアによって分解されるときに消費されますから、たとえば富栄養化が進行して、湖底に多くの有機物が堆積した場所は、酸欠になりやすいのです。一方、酸素の供給は、先ほど述べた冬期の循環に依存しています。
最近のように、地球温暖化が進行すると、冬期の気温が下がらなくなり、全循環が発生しなくなるので、湖底まで酸素が供給されにくくなります。溶存酸素の低下は、生物の斃死をもたらすだけでなく、底にたまった栄養塩や重金属の溶出をもたらします。人間で言えば、心不全の手前といえます。琵琶湖が、まさにこのような状況に差しかかりつつあることを、私たちは今、深刻に捉え警告を発しています。

図2 これまで学術雑誌で報告されたデッドゾーンの積算数。
10年毎の階数で表示している。1960年以降は、10年ごとに2倍ずつ増加している。
(Diaz and Rosenberg,2008を改変)
一口メモ
水の混合
水は、なかなか混じりにくい性質を持っています。たとえば、アマゾン川には白い川と黒い川があり、両方の川が出合ってからも、数キロにわたって混じりあうことなく平行して流れます。琵琶湖でも、高時川と姉川が合流すると、色の濃さの違った水がずっと下流まで流れていきます。水が混合するためには、お風呂の水をかき混ぜるように、何かの力が必要です。それは、風の力だったり、水流の強さだったりします。混じりやすい状態のことを物理学では、不安定な状態と呼んでおり、よく混合した水の中では、密度はほぼ一定です。一方、安定な状態の水は混じりにくいといえます。地球温暖化が進行すると、海洋や湖沼の表面水は熱せられて、安定になります。こうして、上下に混合しにくくなるので、底では酸素不足になりやすいのです。
第7話 びわ湖への想い
第4話 深底部での酸素低下はなぜ起こるか
第2話 顕在化するアオコ毒による生物への影響
第1話 琵琶湖に忍び寄る温暖化の波
近年の琵琶湖をめぐる環境課題 vol.6
近年の琵琶湖をめぐる環境課題 vol.5
第4話 深底部での酸素低下はなぜ起こるか
第2話 顕在化するアオコ毒による生物への影響
第1話 琵琶湖に忍び寄る温暖化の波
近年の琵琶湖をめぐる環境課題 vol.6
近年の琵琶湖をめぐる環境課題 vol.5
Posted by びわ湖トラスト事務局 at 16:23│Comments(0)
│琵琶湖