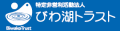第5話 湖底での魚の斃死
2009年12月09日
第5話 湖底での魚の斃死
1.低酸素水塊の形成
2007年は暖冬で、琵琶湖の全循環は不完全なままに春を迎えました。3月中旬になっても、湖底の溶存酸素濃度は、1リットル中に6~7mgまでしか回復しませんでした。3月末には、一時的に9~10mgまで回復しましたが、4月になると表層が加熱され、やがて湖底での酸素消費が始まりました。つまり、十分な深呼吸は起こらなかった可能性があります。
その後、8月から9月にかけての猛暑で、湖底付近の溶存酸素濃度が急激に減少しました。そして、10月から12月にかけての約2ヶ月間にわたって、湖底付近の溶存酸素濃度は、1mg以下の低い数値になりました。
暖冬による全循環の不全によって、湖底に十分な酸素を送り込むことができなかったことと、猛暑によって琵琶湖における上下の水温差が大きくなり、湖底付近の水が停滞したことが、急激な酸素低下をもたらした原因と思われます。
2.イサザの斃死
2007年12月4日から5日にかけて、自律型潜水ロボット「淡探」は、琵琶湖北湖の第一湖盆を調査し、湖底に横たわるイサザとスジエビの死体を発見しました(図)。同時に測定した溶存酸素濃度は、最も低い数値で0.6mg/L以下でした。これは、魚類の半数致死溶存酸素濃度として一般的に言われている2.0mg/L(例えばEPA1986)よりはるかに低い数値でした。淡探が撮影した映像から確認された死亡個体数は、約2kmの移動区間内で、1200匹以上に及びました。湖底上1mを航行する淡探が撮った湖底映像という、きわめて限定した水域の割には、あきらかに多すぎる死亡数でした。
愛媛大学の研究グループは、酸欠以外に死因の可能性を確認するために、死亡個体に含まれる重金属の分析を行いました。その結果、死亡個体の中から高濃度のマンガンとヒ素を検出しました。イサザやスジエビの直接的な死因が、酸欠なのか重金属なのかについては、まだはっきりしません。ただ、1977年に高松武次郎氏らによって指摘されているように、琵琶湖の湖底泥の表面には大量のマンガンやヒ素などが蓄積しています。今後、地球温暖化がさらに進行し、酸素がない水域(デッドゾーン)が拡大すれば、もっと多くの重金属が溶出してくる恐れがあるので、注意が必要です。
琵琶湖の深い場所には、アナンデールヨコエビやビワオオウズムシ、イサザ、ビワマスなどの固有な生物が生息しています。琵琶湖が健全であるためには、これらの固有種を主体とする湖底生態系がうまく機能することが大切です。
3.その後の湖底環境
2008年の冬は寒さが厳しく、琵琶湖の溶存酸素濃度は、1月下旬に回復しました。その後、2月中旬まで冷え込みが続きましたが、2月後半からは暖かくなり、湖底で酸素消費が始まりました。7月になってから気温が急に高くなり、再び湖底の溶存酸素濃度が低下しました。9月になると、デッドゾーンが形成され、ウツセミカジカやイサザの死亡が確認されるようになりました。そして、12月中ごろまで、2mg/L以下の低酸素状態が継続しました。
2009年の冬も暖冬で、3月になっても湖底付近に強い境界層が存在しています。溶存酸素濃度は回復傾向にありますが、全循環が完全には起こっていない可能性もあります。
琵琶湖はこれからどうなるのでしょうか。他の湖沼の事例から見て、湖底付近でいったん低酸素状態が形成されると、なかなか回復しないようです。一般的に言って、湖水が混じりにくくなると、深いところの栄養塩が表層に届かなくなるので、植物プランクトンが減少し、漁獲量は低下します。一方で、深い場所には、底泥から溶出したリンや窒素といった栄養塩がたまり始めます。琵琶湖と同じような状況にあるレマン湖では、すでに低酸素状態が恒常化し、深水層のリン酸態リン濃度は、琵琶湖の10倍にまでなっています。ネパールの湖では、季節風が吹くと深い場所の無酸素水が上昇し、魚が大量に死んだり、深層からの栄養塩の急激な供給でアオコが発生したりしています。
一口メモ
琵琶湖の湖底
琵琶湖の湖底は、平らではありません。水面から見えないところに山があったり、谷があったりします。琵琶湖大橋より北を北湖(ほっこ)、南を南湖(なんこ)と呼んでいます。北湖は安曇川を境に二つの盆地から成り立っており、北の盆地を第一湖盆、南の盆地を第二湖盆と呼びます。第一湖盆は、水深が90m以上あって、第二湖盆より広く、2007年以降、溶存酸素濃度が低くなるデッドゾーンが形成されています。第一湖盆の南端には、湖底から水面下30mまでそそり立つ隠れた山があり、その東麓に、琵琶湖で最も深い場所(104.1m)があります。ここは、酸素が多い時期には、たくさんの生物(ヨコエビやビワオオウズムシ)が集まっており、興味深い場所です。

図中の黒く塗った領域(溶存酸素濃度が低く、魚の死体が見つかった水域)。

2007年12月 琵琶湖湖底で採取された死んだイサザ
熊谷道夫
1.低酸素水塊の形成
2007年は暖冬で、琵琶湖の全循環は不完全なままに春を迎えました。3月中旬になっても、湖底の溶存酸素濃度は、1リットル中に6~7mgまでしか回復しませんでした。3月末には、一時的に9~10mgまで回復しましたが、4月になると表層が加熱され、やがて湖底での酸素消費が始まりました。つまり、十分な深呼吸は起こらなかった可能性があります。
その後、8月から9月にかけての猛暑で、湖底付近の溶存酸素濃度が急激に減少しました。そして、10月から12月にかけての約2ヶ月間にわたって、湖底付近の溶存酸素濃度は、1mg以下の低い数値になりました。
暖冬による全循環の不全によって、湖底に十分な酸素を送り込むことができなかったことと、猛暑によって琵琶湖における上下の水温差が大きくなり、湖底付近の水が停滞したことが、急激な酸素低下をもたらした原因と思われます。
2.イサザの斃死
2007年12月4日から5日にかけて、自律型潜水ロボット「淡探」は、琵琶湖北湖の第一湖盆を調査し、湖底に横たわるイサザとスジエビの死体を発見しました(図)。同時に測定した溶存酸素濃度は、最も低い数値で0.6mg/L以下でした。これは、魚類の半数致死溶存酸素濃度として一般的に言われている2.0mg/L(例えばEPA1986)よりはるかに低い数値でした。淡探が撮影した映像から確認された死亡個体数は、約2kmの移動区間内で、1200匹以上に及びました。湖底上1mを航行する淡探が撮った湖底映像という、きわめて限定した水域の割には、あきらかに多すぎる死亡数でした。
愛媛大学の研究グループは、酸欠以外に死因の可能性を確認するために、死亡個体に含まれる重金属の分析を行いました。その結果、死亡個体の中から高濃度のマンガンとヒ素を検出しました。イサザやスジエビの直接的な死因が、酸欠なのか重金属なのかについては、まだはっきりしません。ただ、1977年に高松武次郎氏らによって指摘されているように、琵琶湖の湖底泥の表面には大量のマンガンやヒ素などが蓄積しています。今後、地球温暖化がさらに進行し、酸素がない水域(デッドゾーン)が拡大すれば、もっと多くの重金属が溶出してくる恐れがあるので、注意が必要です。
琵琶湖の深い場所には、アナンデールヨコエビやビワオオウズムシ、イサザ、ビワマスなどの固有な生物が生息しています。琵琶湖が健全であるためには、これらの固有種を主体とする湖底生態系がうまく機能することが大切です。
3.その後の湖底環境
2008年の冬は寒さが厳しく、琵琶湖の溶存酸素濃度は、1月下旬に回復しました。その後、2月中旬まで冷え込みが続きましたが、2月後半からは暖かくなり、湖底で酸素消費が始まりました。7月になってから気温が急に高くなり、再び湖底の溶存酸素濃度が低下しました。9月になると、デッドゾーンが形成され、ウツセミカジカやイサザの死亡が確認されるようになりました。そして、12月中ごろまで、2mg/L以下の低酸素状態が継続しました。
2009年の冬も暖冬で、3月になっても湖底付近に強い境界層が存在しています。溶存酸素濃度は回復傾向にありますが、全循環が完全には起こっていない可能性もあります。
琵琶湖はこれからどうなるのでしょうか。他の湖沼の事例から見て、湖底付近でいったん低酸素状態が形成されると、なかなか回復しないようです。一般的に言って、湖水が混じりにくくなると、深いところの栄養塩が表層に届かなくなるので、植物プランクトンが減少し、漁獲量は低下します。一方で、深い場所には、底泥から溶出したリンや窒素といった栄養塩がたまり始めます。琵琶湖と同じような状況にあるレマン湖では、すでに低酸素状態が恒常化し、深水層のリン酸態リン濃度は、琵琶湖の10倍にまでなっています。ネパールの湖では、季節風が吹くと深い場所の無酸素水が上昇し、魚が大量に死んだり、深層からの栄養塩の急激な供給でアオコが発生したりしています。
一口メモ
琵琶湖の湖底
琵琶湖の湖底は、平らではありません。水面から見えないところに山があったり、谷があったりします。琵琶湖大橋より北を北湖(ほっこ)、南を南湖(なんこ)と呼んでいます。北湖は安曇川を境に二つの盆地から成り立っており、北の盆地を第一湖盆、南の盆地を第二湖盆と呼びます。第一湖盆は、水深が90m以上あって、第二湖盆より広く、2007年以降、溶存酸素濃度が低くなるデッドゾーンが形成されています。第一湖盆の南端には、湖底から水面下30mまでそそり立つ隠れた山があり、その東麓に、琵琶湖で最も深い場所(104.1m)があります。ここは、酸素が多い時期には、たくさんの生物(ヨコエビやビワオオウズムシ)が集まっており、興味深い場所です。

図中の黒く塗った領域(溶存酸素濃度が低く、魚の死体が見つかった水域)。

2007年12月 琵琶湖湖底で採取された死んだイサザ
Posted by びわ湖トラスト事務局 at 11:30│Comments(0)